DIGS-2002
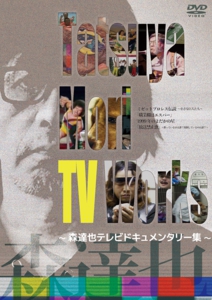
¥7,700
(本体¥7,000)
『Tatsuya Mori TV Works〜森達也テレビドキュメンタリー集〜』
鬼才森達也による伝説のテレビドキュメンタリー4作品が奇跡の一挙DVD化!
◎『A』(1998年)、『A2』(2001)、
『311』(2011)、『FAKE』(2016年)、
『i-新聞記者ドキュメント-』(2019年)....常に話題作、そして問題作を発表する映画監督森達也が
テレビドキュメンタリー史に鋭く刻んだ
伝説の傑作4番組を奇跡のDVD化!
■DVD版の予告編は こちら
2枚組DVD/セルのみ
※権利の都合上、一部楽曲を差し替えておりますが、
『放送禁止歌』はOA時と同じ楽曲ノーカットバージョンで収録しております。
封入特典:長与千種、東野幸治、デヴィ夫人、小室等と森達也の
対談を収録したブックレット「四人と語る森達也」(森達也書き下ろし寄稿文収録)
【DISC1】
●『ミゼットプロレス伝説〜小さな巨人たち〜』(1992年9月30日放送/77分)
日本のプロレス黎明期には興業の花形として、またはお茶の間の人気者として一世を風靡した存在でありながら、いつのまにかメディアから黙殺され忘れられた存在となった小人プロレス…唯一現役で活動していた2人(リトルフランキー、角掛ひとし)のもとにかつて逃げ出した選手がまた復帰を願い出た。OBたちも続々集まってきて、実に30年ぶりにテレビマッチ−それはまるで小人プロレスオールスター戦−が実現する。
小人レスラーが語るプロレスラーとしてのプライドとスキル、全日本女子プロレスの会長やレスラー達からのリスペクト、愛情を丹念に描いた傑作。森達也は実現不可能と言われていたこの企画を通した後にプロデューサーに回り、ディレクターには後に『こどもの時間』で映画デビューする野中真理子を起用した。
●『職業欄はエスパー』(1998年2月24日放送/47分)
ドキュメンタリー映画『A』の編集作業と並行する形で、撮影・編集が進められた作品。秋山眞人(超常現象研究家)、堤祐司(ダウジング)、清田益章(スプーン曲げ)ら、エスパーを職業に選んだ3人の超能力者の日常を寄り添って描いた逸品。彼らの超能力は本物なのか、彼らは嘘をついていないのか、そして森達也は彼らを信じているのか…カメラjが徐々にあぶりだしていく。企画自体は、1993年に一度正式に決まりかけたが、清田益章がカメラの前でスプーン曲げを披露することを拒絶してロケ途中で頓挫した作品。その間の経緯や彼らと撮影者である森達也との愛憎も含めてのルポ『スプーン』が2001年に出版された。
【DISC2】
●『1999年のよだかの星』(1999年10月2日放送/53分)
醜い容姿のために仲間から嫌われ居場所を失った鳥「よだか」を描いた宮沢賢治の童話「よだかの星」にインスパイアされた形で動物実験を扱った作品。人間の日常生活に必要な化学物質の商品化の際に義務づけられる動物実験だが、薬品や化粧品等の大手クライアントが公にしていない影の部分に触れることになるため、テレビ業界ではタブー視されている。本作は動物実験反対だけの立場ではなく、動物実験は人類のために必要とする研究者、新薬を必要とする難病患者、動物実験絶対反対の愛護団体の葛藤を各々描くことで、森達也らしい白と黒の間にある矛盾をはらんだ「生」が提示されていく。
●「放送禁止歌」〜唄っているのは誰?規制するのは誰?〜(1999年5月22日放送/52分)
ドキュメンタリー映画『A』発表後最初の作品であり、森達也の名前をさらに高めることとなった衝撃作。
公序良俗に反する、差別を助長する…様々な理由で放送を見送られる「放送禁止歌」。「なぜ放送されないのか」、「誰が規制をするのか」を森は追う。その過程で、最大の放送禁止理由と言われる部落差別問題を確認すべく直接部落解放同盟本部へと向かう。そして、身内ともいうべきテレビ局へも森はカメラを向ける…。企画自体は6年越しの企画。各局ドキュメンタリー番組担当からは「放送禁止歌を放送できるわけがない」と一蹴され続ける。ようやくフジテレビでの放送が決まり撮影を進める中、「放送禁止歌」とは形骸化したもので、実体などないことがわかる。そこから企画は「過去の規制の検証」から「現在の規制の主体を炙りだす」ことに徐々に変質してゆく。放送後、解放出版社から部落差別問題についての取材を加える形で、同名の「放送禁止歌」として出版された。
※OA時と同じ楽曲ノーカットバージョンでの収録となります。
スタッフ&キャスト
◎『ミゼットプロレス伝説〜小さな巨人たち〜』
制作:フジテレビ、K2 mesh/ナレーター:益田由美/演出:野中真理子
プロデューサー:森達也、木村可南子
◎『職業欄はエスパー』
制作:フジテレビ、グッドカンパニー/プロデューサー:生野耕一
演出・撮影・ナレーター:森達也
◎『1999年のよだかの星』
制作:フジテレビ、グッドカンパニー/ナレーター:石井ひとみ
プロデューサー:渡部宏明/演出・撮影:森達也
◎『「放送禁止歌」〜唄っているのは誰?規制するのは誰?〜』
制作:フジテレビ、グッドカンパニー/プロデューサー:渡部宏明
演出・撮影・ナレーター:森達也
【著名人コメント】※50音順
森達也は日本のドキュメンタリストのなかでも最も迷宮だと思っている。映像作品だけでなく全ての著作、全ての表現がテーマの解釈や判断基準を何時も観客に委ねている。
現実は常に白と黒に分けることはできない。勝ち負けのように二分割されることはないのだ。今まで見たことがない多種多様に多彩な現実を森作品は教えてくれる。
今回、DVD化されたテレビ作品も時代を超えて何度も見ることのできる「森の迷宮」の入り口だ。
水道橋博士(芸人・浅草キッド)
本人の前では言いたくないけれど、森達也という人にはかなりの影響を受けている。物事を裏側から見る人、なんて言えば、君はどうしてそれが裏だと思ったのか、表とは何かと聞いてくるに違いない。この面倒臭さだ。面倒臭さの中に、優しさが垣間見える時があって、それがどうも病みつきになる。その病みつきが、この作品群に詰まっている。
武田 砂鉄(ライター)
森達也の作品には「迷い」がある。これが真実だと突きつける傲慢さは一切なく、心が折れたり、弱音をはいたり、伝えるべきことなのかと悩んだり。取材者の迷いを隠すことなく撮り続ける森達也の映像の中に、観る者自身が真実を探そうとのみ込まれ、正解のない「人間らしさ」の虜になってしまうのだ。
長野 智子(キャスター・ジャーナリスト)
簡単に答えを出したがる、簡単に白黒つけたがる人が増えた今の風潮に完全に逆行した作品群であるが、それでいて、一見センセーショナルな事柄がすべて身の回りの日常に感じられるほどに視線が落ちついている。すべての話が、今に続く長い物語の一部であることを想起させる。登場人物のその後から現在にかけてを調べたくなる衝動に駆られる(実際、調べてしまった)。
能町みね子(コラムニスト)
途方に暮れてしまう。20年前、森達也が「わたし」に突きつけた問い。目を逸らし続けてきたのだろうか。それとも本当に気がつけないほど「わたし」は馬鹿なのか。自己保身が過ぎるし、欲に目が眩みすぎている。それが剥き出しの「わたし」の本性なのだとしたら仕方がない。受け入れるのだ。それで生き延びた私は共犯者だ。だからこそ、この4つの作品はアーカイブ映像ではない。現在進行形のルポなんだ。もう目を逸らすな。まだ繰り返すのか。私は私に怒りを覚えた。現場に行きたい。そして己に突きつけたい。それぞれの「わたし」たちに伝えたい。見るべきだ。
堀 潤(ジャーナリスト)
森達也が一番すごいところはオウムの映画を発表した直後に『超能力者』のドキュメンタリーを撮ったことだ。
宮崎 哲弥(評論家)
どっちの選手が勝つか関係者が賭けていた特殊なプロレス団体、全日本女子プロレスの人気をビューティ・ペアやクラッシュギャルズらと共に支えたのが小人プロレスだ。サーカスでいえばピエロのような役割だとばかり思っていたから、91年発売のビデオ『ミゼット物語』と92年放送の『ミゼットプロレス伝説』(どちらも最高! でも、ビデオ安売王の『ミゼットマニア』はイマイチ!)で全盛期のタッグマッチを見て衝撃を受けた。やたらスピーディで、身体が小さいからこそ全力でリングに叩きつけて激しい音を出し、かなりのリスクを背負って笑いを取る、これこそが“明るく楽しく激しいプロレス”! 全女も、松永会長も、リトルさんも、秩父リングスターフィールドも全てが存在しなくなったいまとなっては、おとぎ話みたいな映像ばかりなのである。
吉田 豪(プロインタビュアー)
©森達也